Made in Japanの心に触れる旅~第6回 夏休みスペシャル
戦国のお城 6-1 石垣~石垣作りのプロ集団・穴太衆(あのうしゅう)の技 Journey to touch the heart of “Made in Japan. The castles in the Warring States period-Technical Professional Group called “Ano-Shu who is the specialist of constructing stone walls.
 ①大阪城 天守閣 Osaka Castle Main Tower, reconstruction, Osaka city 独立式五重五階 復元天守 (大阪府大阪市)城主:豊臣秀吉・秀頼、徳川秀忠 石垣の最下段にあたる根石からの高さが32メートルの上にそびえる天守閣は、全長54,8メートルで日本一。その周りを幅50メートルもある内堀と外堀に囲まれています。日本で一番の難攻不落(なんこう・ふらく)の城と言われていました。守りが堅くて攻めにくく、容易には陥落しない城だったのです。しかしながら、大阪冬の陣で徳川連合軍に堀を埋められ、1620年(慶長20年)大阪夏の陣で落城。現在の大阪城の天守閣は、徳川家康時代の天守閣の再建です。
①大阪城 天守閣 Osaka Castle Main Tower, reconstruction, Osaka city 独立式五重五階 復元天守 (大阪府大阪市)城主:豊臣秀吉・秀頼、徳川秀忠 石垣の最下段にあたる根石からの高さが32メートルの上にそびえる天守閣は、全長54,8メートルで日本一。その周りを幅50メートルもある内堀と外堀に囲まれています。日本で一番の難攻不落(なんこう・ふらく)の城と言われていました。守りが堅くて攻めにくく、容易には陥落しない城だったのです。しかしながら、大阪冬の陣で徳川連合軍に堀を埋められ、1620年(慶長20年)大阪夏の陣で落城。現在の大阪城の天守閣は、徳川家康時代の天守閣の再建です。
➁ケース、ブレスレットの造形美がどこか石垣の上に建つ城のようにも思えるZT007SBKと大阪城 The case and bracelet of the ZEROO T7 watch are “formative art” which looks like the castle on the stone walls.
<0.大阪城と大阪の地形について>
かつての大阪の北西部、淀川の南に広がる一帯は、低湿地帯でした。現在のJR大阪駅周辺は、田畑を耕作する為に、埋め立てられたので、「埋田(うめだ)」が、いつしか「梅田」と美称で呼ばれるようになったのです。
現在も梅田のビル街は、地盤が弱い為、地下30メートルにも及ぶ”梅田粘土層“の下の固い岩盤まで掘り進めて、長い杭を打ち込んでいます。
大阪城は、湿地帯ではなく、固い地盤の上町台地の先端に建てられています。元々は、石山本願寺の跡地で、織田信長がこの地を見出し、土木工事の名手・豊臣秀吉によって大阪城がつくられ、城下町と共に発展していきました。
<1. 戦国時代の山城>
城の起源は、諸説ありますが、中国の唐との戦いに敗れた天智天皇が太宰府に日本の防衛の為に664年に作らせた水城(みずき)と言われています。水城は、高さ9メートルの土塁と水堀を備えていました。
時計の起源は、671年に天智天皇が漏刻(ろうこく=水時計)を造ったのが始まりと言われています。その日を太陽暦に直すと6月10日ですので、日本では、「時の記念日」とされています。城の起源と時の起源がほぼ同時期というのは、興味深いですね。
戦国時代初期の城は、山城が中心で、自然にできた地形を利用して、更に山を切り盛りして土塁(どるい=つちの壁)や堀切(ほりきり=山の尾根を削って作った溝)を造り、自然の要害とした軍事施設でした。
漢字の造りの「城」の文字通り、「つち(土)からなる(成)」建物でした。掘立柱(地面に穴を掘って柱を立てた)の上に板葺き屋根を乗せた「簡素な建物」が城だったのです。
<1―1 戦国の山城~八王子城>

③八王子城址跡大手門跡Hachioji castle ruins, main gate ruins, Hachioji, Tokyo(東京都八王子市)南関東を代表する戦国時代の山城。土塁(土の壁)の中央に竪堀(溝)が見られます。
山城は、自然の要害を生かし、敵の侵入を防ぐ為、土塁(どるい=土の壁)に土を掘って作った縦堀(たてほり)や横堀、山の尾根をつたって登ってこられないように堀切(ほりきり)と言われる溝を掘って防御としました。
戦国時代以前の山城の起源は、南北朝時代、鎌倉幕府を倒す契機となった後醍醐天皇の倒幕計画に呼応した楠木正成(くすのきまさしげ)の千早城(大阪府)と言われています。元弘3年(1333)、「千早城の戦い」で楠木正成は、鎌倉幕府の大軍と戦い、大劣勢をはねのけて、勝利しました。
それまで、「野戦(平地)」での戦いが主戦場だった鎌倉時代。戦いを初めて「険しい山城」に敵を引き込んで戦うゲリラ戦法で勝利したのです。その後、戦国時代初期からは山城の戦いが主戦場となっていきます。
八王子城は、北条氏の居城・小田原城の支城(本城の周囲に点在し、連携して敵の攻撃に対処する比較的小ぶりな城)として天正15年(1587)後北条氏(小田原北条氏=北条早雲を祖とする鎌倉時代に執権として活躍した北条氏とは別家系)三代氏康の三男・氏照(うじてる)により築城されました。
山の尾根や谷などの天然の要害を使い、石塁(せきるい=小ぶりな石垣)も備えた関東屈指の山城でした。なんと天守は、標高460メートルの山の上にありました。
発掘調査で瓦が一枚も出てこないことから、いわゆる近世の典型的な城のように石垣の上に建てられた瓦葺きの天守閣は、なかったと考えられています。
秀吉の小田原攻めの際、八王子城は、前田利家・上杉景勝軍に攻められ落城しました。
現在の八王子城址は、御殿につながる石塁を備えた虎口(こぐち:攻められにくいよう狭くした入口)など一部が復元されています。

④八王子城 模型 Hachioji model castle八王子城は、山の尾根や谷など複雑な地形を利用して造られました。
山頂の本丸(写真左上・軍事エリア=標高約460メートル)と山麓の御主殿(ごしゅでん/写真右下・生活エリア=標高約220メートル)の他、尾根で敵を食い止める平地(城の用語で曲輪・くるわ=城の区画)のエリア(右上外側部)を作っています。
よく時代劇などで城主が天守閣にいる様子が描かれますが、それは主に戦の時で、籠城戦を強いられている時や落城寸前に最後の防御の砦である天守閣にとどまっている時などです。
基本的に城は、「守り」の為の要塞なのです。
山城の場合、平時は天守閣で生活するのは、不便なので、城主は、たいてい山の麓にある御殿で政務や生活をしていました。

⑤八王子城址・虎口(復元) Hachioji ruins, castle entrance, reconstruction山城ながら、石塁(せきるい=比較的小ぶりの石で、高さもそれほど高くない石を積み上げたもの)を使って造られた堅固な城です。曲輪(くるわ=城の区画)の入口部分の虎口(こぐち)は、幅が狭くなっていて、大人数の敵が一気に侵入できないようになっていました。
戦国時代の城の設計を「縄張り(なわばり=縄を貼って区画を計測したことから)」といいます。転じて現代の用語では、動物が生存するテリトリー(領域)を指すことばですが、
城の用語としては、「城の全体の設計」のことを指します。
曲輪(くるわ)とは、戦国時代の城の縄張りを構成する城の区画の名称の一つ。軍事的な意図を持って、削平・盛土され、外を土塁、石垣、柵や堀などで区画した平面空間を指します。
江戸時代には、「丸」と言い変えられることが多く同義です。天守閣(最後の防御に砦にして城のシンボル)や御殿(城主の居住地域)は本丸、本丸の外側を二の丸、二の丸の外側が三の丸となります。重要度は、本丸>二の丸>三の丸です。
西の丸(方角)や真田丸(さなだまる/真田信繫から)などと方角や人物の名前がつけられることもあります。
本丸をどこに置くか、二の丸・三の丸などの曲輪(くるわ=城の区画)はどう配置するか、防御のための堀や土塁はどうめぐらせるかなど、城全体の設計が「縄張」です。モノや範囲ではなく、軍事施設としての城を設計すること、そして城の構造そのものを意味しているわけです。
<八王子の地名の由来>
平安時代、華厳菩薩妙高和尚というお坊さんが、牛頭天皇(ごずてんのう=インドの祇園精舎の守護神)からお告げを受けて、牛頭天皇と八人の王子を「八王子権現社(はちおうじ・ごんげんしゃ」として、深沢山(ふかざわやま)に祀りました。
北条氏照が深沢山に城を築く際に、城の守り神として、八王子権現社を祀った為、城は、「八王子城」と呼ばれるようになりました。これが「八王子」の地名の起源と言われています。

⑥八王子城址 石垣跡 土の中に400年もの間、崩れずに残っていた貴重な築城当時の石垣。Hachioji ruins, stone walls berried in the earth from 400 years ago with remaining original structures.
八王子城は、戦国時代に築城された石塁/石垣を使った関東屈指の山城です。
八王子城の石垣は、山を削って曲輪を作る過程で出てきた石(硬質砂岩)を使って造られたものです。自然石を加工せずに積み上げる野面積み(のづらづみ)です。

⑦八王子城址 山頂の本丸跡に近い九合目からは、関東平野を見渡すことができます。
Hachioji Castle ruins. You can look broad-ranging overview of Kanto Plain form the top of the mountain.
<1-2 石垣の起源>
石垣の起源は、土塁などの堀だと言われています。
北条早雲(鎌倉時代の執権の北条氏とは別家系の為、小田原北条氏と区別して呼ばれます)
の小田原城は、北側には、険しい山があり、南側には、大きな水堀。水堀の先は、相模湾となっています。小田原城は、山と海に囲まれた難攻不落のお城でした。
地形を最大限に活かした構造だったことや、敵を小田原城まで到達させないように多数の支城(本城の周囲に点在し、連携して敵の攻撃に対処する小さな城)を持っていたことなどから非常に攻略しにくい城だったと言われている城です。
小田原城は、忍城(おしじょう:埼玉県行田市=豊臣秀吉が唯一落とせなかった城として有名。わずか500人の兵で、2万人の石田三成による水攻めに屈しなかった城。野村萬斎主演映画「のぼうの城」のモデル)、滝山城/八王子城(東京都八王子市)、三崎城(神奈川県三浦市)韮山城(静岡県伊豆の国市)などの支城がありました。
戦国時代の名将・上杉謙信も武田信玄も小田原城を攻略できませんでしたが、豊臣秀吉の小田原攻めで降伏・開城しました。
小田原攻めは、天正18年(1590)豊臣秀吉が天下統一を目論見て、北条氏の拠点である小田原城を攻めた戦いです。秀吉は、22万人と言われる大軍で小田原城を包囲、北条氏は3か月の籠城戦に出ます。
秀吉は、本城の小田原城を総攻撃するのではなく、支城の八王子城を攻めました。北条氏直は、味方に多くの犠牲を出したことで、ついに開城したと伝えられています。

⑧小田原北条氏が多用した障子堀(しょうじぼり)。Castle moats shaped like paper sliding door.障子の桟(さん)のような盛り土部分がある堀。堀の中の横移動を難しくする為の仕掛け。斜面の堀に障壁をつくり、水を入れた為、水堀または泥堀となっていました。障壁と水(泥)に足を取られた敵を攻撃する仕掛けとなっています。

⑨障子堀のイメージ図。Image picture of castle moats, paper sliding door. Clay soil of the moats is slippery for samurai worriers of enemy. 敵の兵士には、粘土質ですべりやすい関東ローム層の特徴を生かした「障子堀」の障壁を作るのを小田原北条氏は得意としました。障子堀の先には、高い土の壁(どるい)があり、城からの集中攻撃を受けます。
石垣は、こうした「土塁が進化したもの」と考えられます。
Stone wall is the evolution from earthen wall.
<2.近世の城と石垣>Castles and Stone Walls of early modern era.(Azchi-Momoyama era).
近世(安土桃山時代)の城は、平地や小高い丘の上に建てられた「平山城」で、天正四年(1576)に築城を始めた織田信長の総石垣の安土城が最初の近世の城と言われています。石垣の上に、櫓(やぐら)を建て、や天守などの巨大な建物を乗せ、瓦の屋根を持つ城がそれ以降つくられました。
櫓/矢倉(やぐら)/は、弓矢や刀を格納する武器庫で、元々「矢倉」と書かれていました。見晴らしの良い高いところに作られる敵に対する見張り台の役目があり、ここから弓矢で敵の侵入を食い止めました。
その後、普請(ふしん=土木工事 建築工事を指す用語。人々に請い,共に力を合わせて労役に従事し事をなすという意から)と縄張り(曲輪や堀をどこに作るかの設計)の重要性が増し、戦国武将の天下統一の戦いと共に築城技術が発展していきます。
<3.石垣の積み方の進化> The evolution of Stone Wall Construction techniques.
元々、土塁の上に築かれていた山城は、石垣の上に建てられることによってより高くなり、
軍事施設ということに加えて、「権威の象徴」として「見せる城」という意味が加わってきました。
石垣は、矢や鉄砲を撃ち込まれても簡単に崩れないような頑丈に作られ、敵に簡単に登ってこられないように、石垣を組む技術の発展のお陰で、より高く、より急勾配に積まれるようになりました。
それでは、代表的な石垣の組み方の変遷についてみてみましょう。
<3-1野面積み(のづらづみ)> 鎌倉時代~戦国時代初期
Random rubble Stone Wall Construction techniques (Stone wall construction of naturally shaped stones)
大小の自然石を積み上げていく、大きな石の隙間はより小さな石(間詰め石)で埋める積み方。
まだ固い石を積みやすいように四角く切る技術が無い時代、自然石を加工せずに石垣を積んでいく野面積み(のづらづみ)は、戦国時代、石垣を積むプロ集団の名前から別名「穴太積み」(あのうづみ)とも称されています。石と石の隙間部分には、間詰石(まづめいし)と呼ばれる小さな石を挟んでいます。

⑩野面積みの石垣 犬山城(愛知県・犬山市) 1537年(天文6年)織田信長の叔父、織田信康により築城。
実は、この不揃いな自然石を巧みに積みあげる方法の野面積みのほうが、隙間が多い為、排水が良くてより強度が高いと言われています。
<3-2 割り石積み(打ち込みハギ)>Fitted cut stone wall construction techniques戦国時代後期(慶長年間)石の接合部分を削ることによって、隙間を少なくした積み方。

⑪割り石積み 丸亀城(香川県・丸亀市)の20メートルもある高石垣。
Fitted cut Stone Wall Construction techniques. Stone wall of Marugame Castle, 20meters height. 1597年(慶長2年)生駒親正・一正により築城。
粗く加工された石を積む「割石積み(打ち込みハギ)」は、慶長年間から作られた技法。
この石垣も石の隙間には、間詰め石を入れていました。
実は、野面積みは、自然石をパズルのように積み上げるという穴太衆(石垣職人)の神業に負うところが大きかったのですが、石を切る技術の発展によって、石積みを学んだ職人が石を積むことができるようになりました。石を切る技術が築城技術の発展に大きく貢献しましました。
<3-3 切り石積み(切り込みハギ)>Deep-cutting stone wall construction techniques 戦国時代後期(慶長年間)以降 石を直線的に加工し、隙間を無くした積み方。
石を切る技術が進化したのは、良いのですが、正方形や長方形のカットされた石を隙間なくブロックのように積んだ「切り石積み(切り込みハギ)」では、石材が密着し、かつ、奥行きが短いのでかえって傷みやすいという性質も出てきました。

⑫切り石積み Deep cutting Stone Wall Construction techniques 金沢城址 玉泉院丸公園(石川県・金沢市)色紙短冊積石垣 1662年(寛文2年)頃の製作と言われています。
<3-4 色紙短冊積(しきしたんざくづみ)石垣~金沢城址>
金沢城址は、同じ城址の中に、時代によって違う技法の石垣が混在しているので、「石垣の博物館」と言われています。
初代の加賀藩主・前田利家の時代の石垣は、野面積みの石垣。
三代・利常(としつね)の時代の石垣は、割石積みの石垣。
五代・綱記(つなのり)の時代の石垣は、切り石積みの石垣と時代によって違う技法の石垣が存在します。
この色紙短冊積み石垣は、「切り石積み」の手法で、五代・綱紀の時代に造られました。
色紙(正方形)や短冊(長方形)の形の石垣からこの名がつけられました。
右上には、V字形の石樋も見られます。
高さや向き、色合いなどにこだわった観賞用石垣。V字の樋からは、水が出ていて滝があったと考えらえており、縦長の短冊形石垣は、滝を表したとも言われています。
石垣は、強度を高める為に、石を横にして積んでいくのがセオリーです。この石垣では、石垣の組み方のセオリーに反する縦型の石が使われて、滝が流れる様を表しています。
加えて、石垣は、本来敵に登って来られないようにする防壁ですが、この色紙短冊積み石垣は、階段状になっていることから「見せる石垣」の要素が強くなっており、戦国から天下泰平(平和)の時代への変遷が見られます。
石垣に使われている石は、金沢城から9キロほど離れた戸室山の石切場から運ばれた戸室石(とむろいし)。
戸室石は火山のマグマが冷え固まった安山岩で、戸室溶岩は、噴出のときの酸化作用で赤色、青色を呈しており、それぞれ、赤戸室(あかとむろ)、青戸室(あおとむろ)と呼ばれています。
色紙短冊積み石垣では、隣り合う石に赤戸室と青戸室を交互に並べて、美しい色のコントラストをつけています。
戦に明け暮れた戦国時代から平和な江戸の世の中になって、石垣の「防御」というより
見せる「装飾」的な意味あいで作られたものと考えられます。

⑬金沢城址 谷積み(割石積みの一種) 石を斜めにして交互に積む積み方。
Kanazawa castle ruins, Fitted cut Stone Wall Construction techniques. Piling stones diagonally.

⑭金沢城址 亀甲積み(切り石積みの一種) 亀の甲のような六角形に切り出した石を積み、見栄えを良くして格式を高めた積み方。
Kanazawa castle ruins, Turtle shape deep-cutting stone wall construction techniques.
<4.石垣を作るプロ集団の技~穴太衆(あのうしゅう)>
Professional group of stone wall construction techniques called “Ano-Shu” .
石垣を組むプロ集団は、穴太衆(あのうしゅう)と呼ばれ、城郭の石垣をつくる専門の技術者として幕府や諸藩に仕え、慶長年間の築城ラッシュの際には大きな活躍を果たしたそうです。
穴太の名は、地名が由来で、近江国・穴太(おおみのくに・あのう=現滋賀県大津市坂本)が発祥とされます。
織田信長が安土城の技術者として穴太衆(あのうしゅう)を抱え、秀吉が継承し、秀吉の家臣の大名に穴太衆が散らばって、全国に広がっていったようです。
豊臣政権の五大老の筆頭、前田利家の加賀藩では、利家が穴太衆を抱え、武士と同様に「穴生」という職を置いていたそうです。
現在でも穴太の技を継承している家系が近江(滋賀)や金沢に存在して、お城の石垣の修復などを請け負っています。
まだ固い石を積みやすいように四角く切る技術が無い時代、自然石を加工せずに石垣を積んでいく野面積み(のづらづみ)は、別名「穴太積み」(あのうづみ)とも称されています。

⑮近江穴太衆の末裔 粟田建設 による「穴太積み」一番上に積んである天端石とパズルのような石組みが美しい。Naturally shaped Stone Wall Construction techniques by Awata construction company who is descendant of “Ohmi-Ano-Shu” Stone Wall construction technique looks like a natural puzzle and top horizontal line stones has natural beauty.
同じ大きさ、同じ形状、同じ重さ の石は存在しない為、石面(ツラ)、石目(石の割れやすい方向)石の上下、石の風化具合を見て積んでいくのだそうです。
石垣も礎石として土台になる「根石」と上に積み上げていく「積み石」と一番上の天端石(てんばいし)とに分かれます。石垣を安定されるために隙間に入れる間詰石(あいづめいし)を使います。

⑯近江穴太衆の末裔 粟田建設 十五代 石頭の粟田純徳(あわた・すみのり)さん
Mr.Suminori Awata, descendant of Omi-Ano stone wall technicians, 15th generation.
穴太衆の祖先が最初に比叡山の延暦寺の石垣を造作。その修復を請け負う現代の匠です。
穴太衆の末裔、粟田氏によると「石垣が何百年の風雪に耐えられる堅牢さの秘密は、実は、石垣の裏側にある」と言います。
その秘密は積み石の比重のかけ方にあって、表面から1/3位奥のところに重力がかかるように設計。排水をよくする為と土が水で膨れて崩壊しないように、積み石の後ろに栗石(くりいし)、や裏込石(うらごめいし)という小石をつめているのですと粟田さん。

⑰石垣の断面図 Cross-sectional view of Stone Wall.
元々、城の縄張り(石垣や堀の位置を含む設計)は、軍事施設である為、敵に漏れてはいけない軍事機密。その為、穴太衆の技は、書面に書き残された記述がなく、口伝で伝えられてきました。
今も現代的な仕事のようにマニュアルはなく、石の積み方は、すべて粟田さんの頭の中にあると言います。
穴太衆に先祖代々伝わる言葉が「石の言葉を聴け」”Listen carefully the voice of the stones.”
粟田さんが祖父の十三代目の仕事を見ていると、本当に石が「ここに置け」と話しているかのようにポンポンはまっていったそうです。どの石がどこに入って、その次はこれと、将棋のように何手も先を読む感じで考えながら見てやっておられたそうです。それを見習い、粟田さんも石をずっと眺めるということを常にやっているとのこと。
粟田さんは修業中、祖父の万喜三さんから、穴太衆積みは人間社会にもつながるところがあると、よく言われていたといいます。
「石垣を組んでいくには、大きい石もあれば小さい石もあり、きれいな石もあれば形の良くない石もある。これは人間社会と一緒だ」
「一人一人に役割があるのと同じで、どんな形の石にも必ず役割があって、無駄なものは一つもないのだから、上手に組み合わせてあげなさい」と言われていたそうです。

⑱竹田城跡(兵庫県・朝来市)石垣が完全に残っている山城跡は全国でも珍しく、高い山の上に石垣が連なる姿は、ペルーの古代遺跡から「日本のマチュピチュ」と言われます。Takeda castle ruins. It is called the Machu Picchu of Japan.
朝霧で「雲海(うんかい)」に城跡が浮かぶ幻想的な風景が見られることもあり、別名「天空の城」とも表現されています。穴太(あのう)流・石積み技法の石垣がほぼ当時のまま残っています。
<5.平城と石垣>
元は山城が中心だった城も、石垣組みの技術の発展により、平地でも要害を築くことが可能になりました。
関ケ原の戦いで、西軍・石田三成と東軍・徳川家康の戦いは、東軍の徳川家康に軍配があがりましたが、その後の大阪冬の陣、夏の陣で豊臣秀頼とその母の淀の君による豊臣政権が崩壊する迄は、軍事的緊張は続きました。その間に、築城が相次ぎ、「慶長の築城ラッシュ」と呼ばれています。この時期に築城された熊本城や姫路城は、過剰とも言える防衛力を備えていたと言われています。
<5-1 石垣の名城~丸亀城>

⑲丸亀城の一二三の石垣(ひふみのいしがき)。石垣がひな壇状に折り重なっていて、
亀山を三重、四重に囲んだ石垣は壮大。現存天守が残る石垣の名城。
丸亀城:1602年(慶長7年)、城主:生駒親正(豊臣秀吉から讃岐一国を与えられた武将)、一正。現在の城は、再建。独立式層塔型
<5-2 海城の高松城址>

⑳高松城址玉藻公園 1588年(天正16年)築城。築城者 生駒親正、城主:松平頼重 設計は、黒田如水、藤堂高虎、細川忠興など諸説あるようです)すぐ近くが瀬戸内海に面した珍しい「海城」。北を海、残り三方を三重の水堀で防御した城。天守台から瀬戸内海を眺めることができます。高松城の水堀は、海水が引かれています。
<5-3 築城名人・加藤清正の熊本城>
熊本城を築城した豊臣恩顧の加藤清正は、*賤ケ岳の戦いで活躍した賤ケ岳の七本槍の筆頭でした。武芸に優れた武将ですが、藤堂高虎と並び、築城の名人としても名が残されています。
*賤ケ岳の戦い:本能寺の変で織田信長が明智光秀によって討たれ、その後の山崎の合戦で
羽柴秀吉が明智光秀を討ち、織田家内部の後継者争いの最終戦である賤ケ岳の戦いで、羽柴秀吉が柴田勝家を破り、秀吉の天下統一に近づいた大きな節目となる戦い。

㉑二様の石垣(にようのいしがき)熊本城(熊本県・熊本市)
右側の石垣は、熊本城の城主が「加藤清正の時代」のもの。左は、「細川氏時代」のもので、技術の向上で、左の石垣のほうが、より急な「扇の勾配」の石垣になっています。角度が急になるにつれて、より敵から登りにくくする効果があります。
高く積み上げるには、石垣の隅石(すみいし:角の石)にノウハウがあります。
右側の石垣は、角の石垣が同じ正方形を積み上げる「重箱積み」
左側の石垣は、角の石垣が、長方形を交互に積み上げる「算木積み」で組んであるので、
右の「重箱積み」より急勾配で積み上げることができるのです。
熊本城の「二様の石垣」は、石垣の積み方の進化によって、より急勾配にすることができたという石垣の進化が一目でわかる非常に貴重な資料です。
<5―4 天下普請(てんかふしん=各大名に築城させた)の名古屋城>
名古屋城は、徳川家が諸大名に銘じて築城させたので、築城の名人・加藤清正は、天守の石垣、他にも福島正則、黒田長政など20名の大名が担当しました。
徳川家としては、石垣の天下普請を各大名に命じることで、財政負担を負わせ、力を削ぐという意図がありました。
しかしながら、そのことで、全国の各大名に築城技術が広まっていくということにもなったのです。

㉒名古屋城天守閣(天守は復元ですが、石垣は現存)こちらの石垣は、加藤清正の天下普請に
(てんかふしん)により造られました。石垣の角にあたる石を隅石(すみいし)と呼びますが、典型的な算木積み。隅石に長方形の石を使い、長方形の石の長辺を互い違いに組む積み方を算木積みと呼びます。
ZEROO編集後記
お城の石垣の記事を書くきっかけになった本があります。
2021年に直木賞を受賞した今村翔吾氏の著作『塞王の楯』です。安土桃山時代末期を舞台に、城の石垣を作る「穴太衆」の石工(いしく)の棟梁、飛田源斎が主人公の物語。
鉄砲を作る国友衆を「矛」それを守る石垣を作る穴太衆を「盾」とし、その激しい攻防を描いています。
池波正太郎氏の作品にも石垣の専門集団「穴太衆」は登場しますが、それが主人公になった本は、今までなかったのではないでしょうか。
近江(滋賀県)に穴太衆の末裔の方が、代々石垣を組む仕事を続けられていることも初めて知りました。
戦国時代から全国各地に残る芸術的とも言えるお城の石垣。石を切る技術がまだまだ発達していなかった時代に「石の声」を聴き、パズルのような石垣を組んでいた穴太衆の技。
たとえ、城の天守などの建物が消失したとしても、穴太衆の魂が宿り、時代によって進化していった現存している多くの堅牢な石垣。
これぞMade in Japanの技だと思った編集部でした。
 |
ゼロタイム八王子工房
東京都八王子市長沼町104番地 2-1-3※
※一般の方のご訪問はご遠慮いただいております。
ZEROO TIME Co. Hachioji Atelier ※
We kindly ask end-customer refrain from visiting the facility.
近隣のZEROOショップ
 |
| 阪急メンズ東京 FORTUNE TIME 東京都千代田区有楽町2-5-1 阪急メンズ東京 B1F TEL:03-6252-5448 (直通) 営業時間:平日12:00~20:00/土日祝 11:00~20:00 定休日:不定休 https://www.gressive.jp/shop/R0675 HANKYU MEN'S TOKYO FORTUNE TIME 〒100-8488 B1F, HANKYU MEN'S TOKYO, 2-5-1 YURAKUCHO, CHIYODA-KU, TOKYO TEL: 03-6252-5448 (DIRECT LINE) Closed: No regular holidays. Opening hours: 12:00-20:00 weekdays / 11:00-20:00 weekends and public holidays. https://www.gressive.jp/shop/R0675 |
 |
| 阪急メンズ大阪 THE TIME HOUSE 大阪府大阪市北区角田町7番10号阪急メンズ大阪B1F TEL:06-6361-1381 (大代表) 営業時間:平日11:00-20:00 / 土日祝 10:00-20:00 定休日:不定休 HP:https://www.gressive.jp/shop/R0516 HANKYU MEN'S OSAKA THE TIME HOUSE 〒530-0017 HANKYU MEN'S OSAKA B1F, 7-10, KAKUDACHO, KITA-KU, OSAKA TEL: 06-6361-1381 (MAIN). Closed: No regular holidays. Opening hours: 11:00-20:00 weekdays / 10:00-20:00 weekends and public holidays. https://www.gressive.jp/shop/R0516 |
 |
|
A.M.I 名古屋PARCO店 zip code 460-0008 |
 |
| WING 金沢店 石川県金沢市片町1-3-15 TEL:076-223-5582 営業時間:平日12:00~19:00 休祝日11:00~19:00 定休日:水曜日 WING KANAZAWA 1-3-15, Katamachi, Kanazawa, Ishikawa 920-0981, Japan TEL: 076-223-5582 Hours: 12:00-19:00 weekdays, 11:00-19:00 Closed: Wednesday |
 |
|
WING イオンモール白山店 WING AEON MALL HAKUSAN |
 |
| EYE-EYE-ISUZU G-Time店 香川県高松市丸亀町7-16 丸亀町グリーン西館2F TEL : 087-873-2335 FAX : 087-873-2445 営業時間/年中無休 ※1月1日を除く 11:00~20:00 HP: https://www.eye-eye-isuzu.co.jp/pages/watch-zeroo EYE-EYE ISUZU G-Time Store 7-16 Marugamemachi, Takamatsu City, Kagawa, 760-0029 Japan Marugamemachi Green West Building 2F TEL: 087-873-2335 FAX: 087-873-2445 Open all year round 11:00-20:00 except January 1 HP: https://eye-eye-isuzu.co.jp/gtime/ |
 |
| EYE-EYE-ISUZU本店 香川県高松市多肥下町1523-1 TEL : 087-864-5225 FAX : 087-864-5133 営業時間/定休日:毎週水曜日 11:00~19:30 HP: https://www.eye-eye-isuzu.co.jp/ EYE-EYE-ISUZU HONTEN 1523-1 Tahishita-cho, Takamatsu City, Kagawa, 761-8075, Japan TEL: 087-864-5225 FAX: 087-864-5133 Business hours/Closed: Every Wednesday 11:00-19:30 HP:https://www.eye-eye-isuzu.co.jp/ |


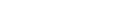











![[NEW] ZEROO M5-01 THE KIRCH MECHANICAL AUTOMATIC](http://zerootime.com/cdn/shop/files/ZM005-01SSV_{width}x.png?v=1753693052)










