Made in Japanの心に触れる旅~第6回 戦国のお城 その2
天守閣~現代の匠が手掛ける狩野派・復元模写の日本画の襖絵。Journey to touch the heart of “Made in Japan. The castles in the Warring States period chapter 2: “Castle Towers and a reproduction of a Japanese sliding screen paintings of Kano school artist by a modern master artist”.

① 世界遺産:姫路城 (白鷺城)兵庫県姫路市 法隆寺と共に日本で最初に世界遺産に認定。現存十二天守閣・国宝五城※のうちの筆頭格。Himeji Castle(White Heron Castle), Himeji-city, Hyogo-Pref. First World Heritage Site in Japan with Horyuji temple. articulated tower building, square-jointed style, Six-stories tower buildings with basement and five roofs, watchtower style. Existing(original) castle tower/national treasure.1580年築 連立式望楼型 5重6階地下1階(1609年再建)現存天守閣/国宝 主な城主:赤松貞範、黒田重隆(軍師・黒田官兵衛の祖父)、羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)・池田輝政(徳川家康と姻戚関係。姫路城を大改築)
※現存十二天守閣とは、江戸時代以前に建てられ、現在残っている12の天守。弘前城(青森県)、松本城(長野県)、丸岡城(福井県)、犬山城(愛知県)、彦根城(滋賀県)、姫路城(兵庫県)、松江城(島根県)、備中松山城(岡山県)、丸亀城(香川県)、松山城(愛媛県)、宇和島城(愛媛県)、高知城(高知県)このブログに6天守閣が登場します。
国宝五城とは、江戸時代以前に建てられた現存天守を持つ城であり、その歴史的価値と建築的価値から国宝に指定された城のこと。姫路城、松本城、彦根城、犬山城、松江城。このブログに4城が登場します。

➁ 姫路城(別名 白鷺城)とT7 Himeji Castle with ZEROO T7 watch , ZT007SBK 姫路城は、敵の侵入を防ぐ為、天守に回廊を通していくつもの櫓が続く複雑な連立式と呼ぼれる城です。複雑時計のトゥールビヨンのムーブメントを搭載するT7。時計の複雑なムーブメントが難攻不落の複雑な構造の姫路城を連想させます。Himeji Castle is a complex castle with a number of towers connected through corridors to the castle tower to block the enemy. The T7 is equipped with a tourbillon movement, a complex watch. The complex movement of the ZEROO watch is associate with the complex structure of Himeji Castle.
池田輝政は、関ケ原の戦いで徳川家康の東軍に味方し、活躍したことで、播磨の国を与えられ、姫路城主となりました。
関ケ原の戦い以後も、徳川家と豊臣家とそれぞれの恩顧の大名の間に軍事的な緊張は続いていました。
池田輝政もその一環として姫路城の改築に着手しました。姫路城の壮大な改築は、豊臣秀頼や豊臣恩顧の西国大名を牽制する意味がありました。 徳川家康は、豊臣家を警戒しており、輝政に姫路城の大改築を命じることで、西国大名に対する抑止力としたと言われています。
当時の江戸幕府(徳川家康)は、諸大名に命じて江戸城の拡張工事(天下普請)を行っており、こうした時代背景によって、「慶長の築城ラッシュ」という築城ブームが巻き起こります。
姫路城は、その白く輝く外観から「白鷺城」と呼ばれています。美しい白漆喰の壁と連立式の複雑な構造の屋根が、白鷺が羽ばたく姿を連想させることからそう呼ばれています。
日本にある現存の12天守閣のうちでも、とりわけ保存状態が良いのは、外観と天守に続く連立式の櫓や回廊があまりに複雑で見るからに難攻不落で、一度も戦場になったことがないことが影響しています。
<1.近世の城の特徴>
近世の城は、平地や小高い丘の上に建てられた「平山城」で、天正四年(1576)に築城を始めた織田信長の総石垣の安土城が最初の近世の城と言われています。石垣の上に、櫓(やぐら)や天守などの巨大な建物を乗せ、瓦の屋根を持つ城がそれ以降つくられました。

③ 大阪城 模型 Osaka model castle. 安土城の「見せる城」を引きついだ黒漆喰の壁に金箔瓦の天守閣の城。石垣を高く積む築城技術の発達で、より高い、勾配の急な石垣と鉄砲の照準距離を考慮した広い幅の水堀の城が造られました。
内堀の外周に広大な外堀があり、土を盛り上げた土塁と水堀の中に城下町を抱えるこのような城の形状を「総構え」と呼びます。籠城戦による食料確保や、洪水から町を守る堤防の役目もありました。

④ 広島城、模型 Hiroshima model castle天下普請(江戸幕府からの築城命令)によって築城コストを抑えてフォーマット化された城が一般化。広い御殿(城主の居住地)を確保しやすい四角い曲輪、長大な水路と高い石垣をベースにしたシンプルな縄張り(設計)。天守閣も望楼型よりシンプルな構造の層塔型。
<2.近世の天守閣の分類>
城と言えば、城のシンボルタワーの天守閣をイメージする方が多いと思いますが、近世の天守閣にも構造的には、2種類に分かれます。
<2-1 望楼(ぼうろう)型天守閣> Castle tower, Watchtower style.
望楼型天守 安土城以来、慶長期までの天守閣の主流。一、二階建ての入母屋造(いりもやづくり=下部に庇屋根がある構造の屋根で、瓦葺だと重厚感があるので、白や寺の建築に使われる)の建物の上に望楼(物見)を乗せた形で部屋が変則的に積みあがっているのが特徴。

⑤ 犬山城 天守閣 愛知県犬山市 Inuyama Castle, Inuyama-city, Aichi-Pref. Watchtower style, Four-stories tower buildings with three roofs. Existing original castle tower, national treasure. 城年:天文6(1537)年 織田信長の叔父・信康により築城。現存十二天守閣のうち「最古」で「国宝」5天守閣のひとつ。望楼型三層四階。望楼とは、入母屋造の建物の屋根の上に望楼(ぼうろう)(遠くを見渡(わた)すための櫓(やぐら)を載(の)せた形式の建物。高さ24m

⑤-2 犬山城の天守からの眺め。木曽川が外堀の外周の堀の役目をしています。
View from tower of the Inuyama Castle. Kiso-river play a role of another outer water moat.

⑤-3 犬山城に続く参道にある茶屋の田楽。Dengaku at a teahouse on the approach to Inuyama Castle.江戸時代には、東海道沿いの茶屋で旅人が田楽を食べたと言われています。田楽の名前は、田植えの時期に行われる豊作を祈る伝統芸能の「田楽神楽」に由来。この舞で用いられる踊り子の衣装が豆腐を串に刺して味噌を塗った料理に似ていることからそう呼ばれるようになりました。It is said that in the Edo period, travelers ate dengaku at teahouses along the Tokaido road. The name “Dengaku” comes from the traditional performing art "Dengaku Kagura," which is held during the rice planting season to pray for a good harvest. The dancers' costumes used in this dance resemble a dish of tofu skewered and smeared with miso paste, this is the origin of the name.
<2-2層塔型(そうとう)天守閣> Multi-tiered castle tower style(The size of the layers gradually decreases as you go up)
慶長以後、築城の名手・藤堂高虎(とうどう・たかとら=築城の三名手として、黒田如水(官兵衛)、加藤清正と並んで名高い)が考案した層塔型がスタンダードに。
一階から最上階まで同じ型の部屋を規則的に逓減(ていげん=徐々に小さくする)させ、積み上げた費用を安く抑える為のシンプルな構造が特徴。最上階になるにつれて、辺の長さが逓減される構造の五重塔の建築の手法を取り入れたものと思われます。

⑥ 小倉城 天守閣(復元)福岡県北九州市小倉北区 Kokura Castle, Kokura-ward(district), Kita-Kyusyu-city, Fukuoka-Pref. Multi-tiered castle tower style築城年(オリジナル):慶長7(1602)年 再建 築城者:細川忠興 連結式層塔型4重5階 高さ28.7m
<築城の名手・加藤清正の熊本城>
関ケ原の戦いで、西軍・石田三成と東軍・徳川家康の戦いは、東軍に軍配があがりましたが、先述の通り、その後の大阪冬の陣、夏の陣で豊臣秀頼とその母の淀の君による豊臣政権が崩壊する迄は、軍事的緊張は続きました。
関ケ原の戦いの後、豊臣恩顧の大名(加藤清正・福島正則など)が増封して、配置換えになると、諸大名はこぞって自領に近世の城郭を築きました。
更に、徳川幕府による「天下普請」が始まって、築城技術が進歩し、完成度の高い城が全国に築かれました。
天下普請を担った藤堂高虎(築城の名手として、浅井長政、豊臣秀吉に仕えた後に徳川家康にも仕えた)は、四角い曲輪と広い水堀、枡形小口と層塔型天守など規格化された築城を実施しました。
その後、元和の一国一城令(徳川家康が各大名の軍事力を削ぐために本城以外を破棄する旨を定めた法令)により、築城が激減していくまで、近世城郭は全国に普及していきます。
その間に、築城が相次ぎ、慶長の築城ラッシュと呼ばれています。
天守閣の構成には、大きく分けて4つに分かれます。
<独立式>天守に付属建築がつかず、単独で建つ形式。直接天守に入ることができる。宇和島城、丸岡城、高知城など。
<複合式>付櫓(つけやぐら)や小天守(しょうてんしゅ)に直結された形式。それらを経由しなければ、天守に入れない。最も多い形式。彦根城、松江城、岡山城など。
<連結式>天守に渡櫓(わたりやぐら)で小天守を接続する形式。小天守を経由しなければ、天守に入れない。松本城、名古屋城など。
<連立式>天守と2基以上の付属建築、または隅櫓を渡櫓でロの字型に接続させる形式。
伊予松山城、姫路城など。

⑦ 天守閣の構成~4つの方式 4type of the structure of the Japanese castle towers.
独立式 independent tower building style
複合式 complex tower building style
連結式 articulated tower building style
連立式 articulated tower building, square-jointed style

⑧ 丸亀城 香川県丸亀市 Marugame Castle , Marugame-city, Kagawa-Pref. independent tower building style, Three-stories tower buildings with 3 roofs.独立式層塔型三重三階 1660年築城者:生駒親正

⑨ 名古屋城 愛知県名古屋市 Nagoya Castle, Nagoya-city, Aichi-Pref. articulated tower building style Five-story building with 5 roofs with basement floor連結式層塔型5層5階地下1階 築城年 慶長14年(1609年)1959年SRC(Steel Reinforced Concrete鉄筋コンクリート)造・外観復元)築城主 徳川家康

⑩ 松本城 長野県松本市 Matsumoto Castle, Matsumoto-city, Nagano Pref. complex-articulated tower building style, Six-stories buildings with Five roofs.複合連結式層塔型5重6階(1633年改)城主:石川数正・康長父子 現存12天守閣、国宝5天守閣のひとつ。
複合式と連結式が合体したお城。複雑時計のような佇まいの荘厳なお城です。
天守閣と月見櫓(写真左の朱塗りの欄干の廊下のある建物。風流な景色や月見や宴を愉しむための櫓)が連結している珍しい形の城。
This castle has an unusual shape, with the castle tower and Tsukimi Tower (the building with the red-painted handrail corridor on the left in the photo; a tower for enjoying the elegant scenery, moon-viewing, and banquets) connected.
月見櫓は、後からの増築。江戸幕府から城の増築は、謀反の誤解を受ける為、厳しく監視されていた為、「風流の為の櫓」と言い訳したとも平和になってきたことの象徴とも言われています。

⑪ 伊予松山城愛媛県松山市Iyo-Matsuyama Castle, Matsuyama-city, Ehime Pref. articulated tower building, square-jointed style, 連立式層塔型3重3階地下1階 築城年 慶長7年(1602年)(1852年再建)築城主 加藤嘉明
<天守閣の外壁~黒い城と白い城~秀吉 vs. 家康>
お城には、白いお城(天守閣)と黒いお城(天守閣)があるのは、何故でしょうか?
時代的な流れもありますが、黒いお城は、秀吉とその恩顧大名の城、白いお城は、徳川家康とその関わりの深い大名の城に分かれるのです。
<黒い天守~豊臣秀吉>
黒い天守の「下見板張り」です。秀吉の家臣たちが築いた城の多くが黒い城でした。
黒い壁となるのは、黒漆喰や黒い漆を塗った板で覆って雨水を防ぐため。 つまり防水機能のためです。
黒には敵から隠す効果もあり、豊臣秀吉の戦国時代には敵から見つかりにくく小さく見える黒い城が建てられたようです。
さらに秀吉は、大坂城などに金箔瓦を好んで使います。黒い板に金箔が映えてさぞ美しかったと思われます。
現在の大阪城は、秀吉の大阪城の石垣の上に建てられた家康の城を再現したもので、
元々の秀吉・大阪城は、信長の安土城の意匠に似せて作られました。

⑫ 秀吉の大坂城(CG)。Osaka Castle computer grafics豊臣秀吉の大阪城は、木の板が黒く塗られた「黒い天守」でした。
ドラマ・映画での時代劇では、CGでこの黒い秀吉・大阪城が描かれています。
現在の大阪城は最上階の壁面だけが黒く塗りこめられ、金箔の虎のレリーフが映えています。その他は白漆喰塗籠ですが、大阪城に展示されている「大坂夏の陣図屏風」を見ると真っ黒な天守が描かれています。
熊本城(加藤清正)、松本城(石川数正/秀吉の家臣時代に造った城)、広島城(毛利輝元/福島正則)、岡山城(宇喜多秀家)などが豊臣恩顧の家臣の「黒い城」です。

⑬ 熊本城 Kumamoto Castle, Kumamoto-city, Kumamoto-Pref. articulated tower building style, watch-tower style, Six-stories tower building with three roofs. 熊本県熊本市 連結式望楼型3重6階(再建) 築城年1469年 改修年 1600年(慶長5年) 城主:加藤清正、細川忠利他。2016年4月の熊本地震の際、際に、多くの石垣が崩落したほか宇土櫓などの文化財建造物、大小天守などの復元建築が被災。現在も修復が進められています。
熊本の地名は、元々「隈本」の表記でしたが、加藤清正が熊本城を築城した際に地名も「隈本」に改名されたと言われています。

⑭ 松本城 長野県松本市 Matsumoto Castle, Matsukomo-city, Nagano-Pref. complex-articulated tower building style, Six-stories buildings with five roofs. existing(original) castle tower, national treasure.複合連結式層塔型5重6階(1633年改)現存天守閣/国宝。城主:石川数正・康長父子(石川数正は、元々徳川家康の重臣の一人でしたが、晩年、徳川家康の家臣となりました)
<白い天守~徳川家康>
関ケ原~慶長以降の徳川家康及び、徳川家康の家臣の城には、白い城壁の「白漆喰 総塗籠」(しろしっくい・そうぬりごめ)天守が作られました。天守の外壁を漆喰で塗り固めて仕上げたもので、全体的に白い外観となります。漆喰は、壁・天井などに使用される塗料で、石灰に、ふのり・粘土などをねり合わせたものです。
実は、黒い壁は、板のままだと水や火に弱いので、白漆喰の壁は、防火と防水のために漆喰で周りを塗り固めた壁です。その上、外観が美しいので、慶長以降人気の外壁となりました。
別名・白鷺城と言われる姫路城では光沢を出すために牡蠣殻の粉を漆喰に混ぜているそうです。
彦根城(井伊直継)、弘前城(津軽信枚)、姫路城(池田輝政)、名古屋城(徳川義直・尾張徳川家)、江戸城(徳川家康・秀忠)和歌山城(徳川頼信・紀伊徳川家)高松城(松平頼重)
などが、徳川家や徳川恩顧の家臣の「白い城」です。

⑮ 彦根城 滋賀県彦根市 複合式望楼型 3重3階地下1階(1604年築). 現存天守閣/国宝complex tower building style, watch-tower-style, Three-stories tower building with three roofs, existing(original) castle tower, national treasure. 城主:井伊直継

⑯ 名古屋城 連結式層塔型5層5階地下1階 Nagoya Castle The golden shachihoko (roof ornament of tiger head with fish body) on the roof of the castle tower is a symbol of Nagoya. 築城年:1615年 1959年外観復元。築城主:徳川家康。城主:尾張徳川家 名古屋城は、織田信長誕生の城とされる今川氏築城の那古野城(なごやじょう)の跡周辺に、徳川家康が天下普請によって築城。
天守閣の屋根の上の「金の鯱(しゃちほこ)」は、名古屋を象徴するシンボルのようなもの。頭が虎で体が魚のインドの神話に登場する怪魚が由来。織田信長が安土城の装飾に使ったのが最初と言われています。魚は、水に通ずることから火事除けの意味もあるとか。
6.<名古屋城御殿と狩野派の復元模写>
TVドラマでは、戦をしている戦国武将が城の最後の砦である天守閣の中で戦っているシーンが多いので、城主が常に天守閣にいるイメージですが、実際は、そんなことは、ありません。
天守閣は、戦(有事)の際に城主が登る最後の砦です。普段は、籠城戦を想定しての兵糧(食料)の「貯蔵庫」としての役割や刀や武具を設置しておく「武器庫」としての役割を担っていました。
平時は、城主も「御殿」に住んでいました。平城の場合、天守閣の近くにあり、山城の際は、山を降りた平地に「御殿」を置き、城主の政治エリア(儀式・家臣との対面・客をもてなす茶室・能舞台など)や生活エリア(城主・正室・側室などが住む場所)として、使われていました。
現存の本丸御殿は、高知城と川越城、二の丸御殿は、二条城と掛川城が残っているだけです。
<6-1名古屋城 本丸御殿>

⑰ 名古屋城本丸御殿(復元)Nagoya Castle , Honmaru-Goten Palace.(Residential Palace of load in near by main castle tower).本丸御殿は、尾張藩主の住居かつ藩の政庁として1615年(慶長20)に完成。1945年の空襲で焼失。その後、総工費150億円をかけ、10年に及ぶ工期を経て2018年に復元されました。
玄関の「虎之間」には煌びやかな金箔の上に描かれた虎や豹の狩野派の襖絵を、現代の匠が復元したものが飾ってあります。

⑱ 名古屋城本丸御殿障壁画 虎図 Nagoya Castle Honmaru Palace Fusuma-sliding screen painting: Tiger, Japanese painting, Kano School painter.日本画史上最大の画派・狩野派(かのうは)の絵師たちが描いてきた障壁画と襖絵(ふすまえ) 狩野派の技法や材質を分析し、当時の色彩を精密に再現。 そのひとつが、まばゆい輝きの金箔の上に描かれた復元画。狩野派の洛中洛外図のように金色の雲のようなタッチでモチーフを引き立てているのが美しい。

⑲ 竹林豹虎図(ちくりんひょうこず) (加藤純子氏・復元模写)襖絵 Leopard and Tiger in the Bamboo Grove (Reproduced by Ms.Junko Kato) 虎と豹が一緒に描かれているのは、江戸時代、豹は虎の雌だと思われていたからと言われています。
力強い筆づかいで、金箔を多用して、豪華絢爛な絵を描いた狩野派の絵師の襖絵(ふすまえ)を見事に再現しています。

⑳ 上段之間(表書院)1615年(慶長20)の創建時には、最大かつ最も格式の高い間として正式に藩主に謁見する際に用いられていました。本丸御殿が尾張藩主の居館だった時の上段之間は藩主の徳川義直が座る部屋で、正式の座敷飾りを揃えています。
<6-2 狩野派の絵を復元模写する現代の匠>A modern master of Japanese paintings who reproduces Kano school paintings.

㉑ 加藤純子氏らによる名古屋城御殿・狩野派の絵の復元作業
Restoration of Kano School paintings at Nagoya Castle Palace by Junko Kato and others
元々の本丸御殿は、狩野貞信や狩野探幽など「狩野派」の絵師により、部屋ごとの題材で、床の間絵や襖絵などが描かれ、豪華絢爛に彩られていました。
戦災により本丸御殿は失われましたが、取り外すことができた襖絵や天井板絵などは、なんと焼失を免れ、保管されていたのです。
「狩野派」の絵師たちが全精力を注いで描いた障壁画の美と色彩感覚を現在によみがえらせるため、加藤純子氏を中心に、当時の絵師が使っていた素材や技法を用いて、顕微鏡やコンピュータ、史料などで研究・分析を重ね、原画と同質の材料で作った和紙に金箔を貼って絵を塗っていく16工程の複雑な作業を行っています。
In order to revive the beauty and sense of color of the sliding screen paintings that the Kano school artists poured all their energy into creating, Ms.Junko Kato and her team are using the same materials and techniques as the artists of the time, conducting repeated research and analysis using microscopes, computers, historical documents, and other tools, and carrying out a complex 16-step process of applying gold leaf to Japanese paper made from the same materials as the originals and painting the pictures.
江戸時代の絵師たちの心を伝える為に、ミクロ単位の観察をもとに緻密な作業が行われていて、なんと、復元模写は、1325面にも及ぶそうです。
In order to convey the spirit of the Edo period artists, meticulous work was carried out based on microscopic observation, and an astounding 1,325 reproductions were created.

㉒ 加藤純子(かとう・じゅんこ)氏 東京芸術大学大学院日本画修了
Ms.Junko Kato (graduated from the Tokyo University of the Arts Graduate School of Japanese Painting) 主な復元模写78年「源頼朝像」、85~98年「瑞巌寺(ずいがんじ) 障壁画」、2003~05年「源氏物語絵巻」1992年(平成4)名古屋城本丸御殿障壁画「竹林豹虎図」復元模写
そもそも模写には、「保存すべき原本の代わりに設置や活用をすることで名作を災害などから守る」という実用的な側面があると加藤氏は、言います。
復元模写は、「古色模写(絵の具の変色や汚れなど経年変化も含めた現状を模写)=レプリカ」と違い、「制作当時の状態を想定した模写」なのです。
Kato says that copies have a practical aspect in that they can protect masterpieces from disasters by being installed and used in place of the originals that should be preserved.
Restoration copies are different from "antiquity copies (a replica which copy the current state, including changes over time such as discoloration of the paint and dirt)", Restoration copies are "copies that imagine the condition they were in at the time they were made."
加藤氏は、続けます。「復元模写は、原本の作品から受けた質の高い感動を表現するもの」で「原画から受けた感動を復元模写に表現する」ように心がけているといいます。
Kato continues, "Restoration reproductions express the high quality of the emotions felt by the original work," and says that he strives to "express the emotions felt by the original in the reproduction."
まず、原画を熟覧して、その時の感動を実現していくというプロセスに始まり、写真などから線描などをトレースして雁皮紙(がんぴし・絵画に使う特別な紙)や竹紙(ちくし)などに写していきます。
その過程は極力、当初と同じ材料、技法、プロセスで描いていきます。紙も科学的に紙質調査をして特別に漉(す)いた物を使うそうです。
長い年月の間に傷んだり、修復で付け加えられたりしたものを排除して、当時の人が目指した美しさに必死になって迫っていきます。独りよがりに解釈することは許されません。当時の画家が目指したものに自分が同化していくような、それが自分の感動でもあるような、その両方が合体した視点が復元模写には必要です。
We must eliminate the damage that has occurred over the years and the things that have been added during restoration, and strive to capture the beauty that the artist originally aimed for. Self-centered interpretations are not permitted. A restoration and reproduction requires a perspective that combines both the artist's own assimilation of what the artist originally aimed for and the artist's own emotions.

㉓ 二条城の二の丸御殿。国宝。世界遺産。部屋数33、約800畳という広大な空間に狩野派による障壁画や、極彩色の彫刻や金の装飾など、豪華絢爛な造りの建物。慶長8年(1603)に、徳川家康が将軍上洛の際の宿泊所として築かれた。江戸幕府最後の将軍、徳川慶喜が大政奉還を表明した場所でもあります。
Nijo Castle's Ninomaru Palace. National treasure. World Heritage Site. With 33 rooms and a vast space of about 800 tatami mats, it is a gorgeous structure with Kano school paintings on sliding screens, richly colored sculptures, and gold decorations.
<編集後記>
お城巡りが趣味の方から、「日本百名城のうちすでに50箇所を行った」という話をよく聞きます。戦国時代に2万~3万あったお城は、一国一城令で廃棄されたり、焼失などでなくなったりして、一般的に見学できる城は、二百ほど。現存天守閣は、たった十二しかありません。
お城巡りの醍醐味は、やはり天守閣。現存十二天守閣は、幾多の戦乱を切り抜けて残っている奇跡の城の数々です。その十二天守閣の中でも、何故、白い城と黒い城があるのかという疑問から紐解いていくと、時代背景や築城技術の発展だけでなく、城主の派閥など色々なことが浮き彫りになってきました。城の構造の分類も知った上で、お城巡りをしたほうがより面白そうです。
城のシンボルタワーである天守閣は、戦の時のもので、一方、城主が平時に居住していたのは、「御殿(ごてん)」です。現存する御殿は、高知城と川越城の本丸御殿、そして二条城と掛川城の二の丸御殿二条城の四つのみです。
子供の頃に行った姫路城と二条城が同じものに見えなかったのは、天守閣や櫓が残っている姫路城と二条城の天守は焼失して、現在、二の丸御殿が見学のメインとなっているからでした。
名古屋城・本丸御殿の再建プロジェクトの目玉は、狩野派の絵師の煌びやかな「復元模写」の絵でした。復元模写は、プロジェクトの中心メンバーの加藤氏によると、先人の匠の技を詳細なデータや検証を通して、現代に蘇らせるために描かれたというだけでなく、原画の感動を伝えるという役割を担うものだったのです。まさにMade in Japanの匠の技です。
二条城の復元模写を説明してくれた職員の方にお聞きしたのですが、二条城の復元模写の絵は、「描かれた100年後の経年劣化を経た」想定で、描かれているそうです。
なぜならば、「400年以上前の現存する二条城の二の丸御殿の鄙びた建物に、新しく描かれたままの煌びやかな絵はそぐわないから」だそうです。そういえば、二条城の襖絵の復元模写の金箔は、名古屋城の本丸御殿のものと比べると若干くすんでいた気がします。
「名古屋城の本丸御殿は、御殿そのものが新しく建てられたものなので、復元模写も描かれた当時の煌びやかなままの狩野派の絵になっている」とのこと。
名古屋本丸御殿の復元にかかった総費用150億円のうち、50億円は、市民の寄付からだそうです。日本は、欧米に比べて、個人が文化を支援する寄付や企業が文化を擁護するメセナ活動は、非常に遅れていると揶揄されがちですが、私たちの知らないところで、徐々に活動が芽生えているようです。
文化財一般に「現存」にこだわる方もいらっしゃるかもしれませんが、名古屋城御殿の復元模写の絵は、当時の狩野派の煌びやかな世界を感じられる素晴らしいものです。
100年後の未来の方が見たらどう思うのでしょうか。もはや現存/復元を超えたひとつの芸術品としてご覧になるのではないかと想像してしまいます。
「職人は、技術を継承し、見る人は、文化を継承する」と言われるように、見る私たちは、
こうした文化を継承していく手助けをする役割があるのではないでしょうか。イタリア・ルネッサンス風に言えば「パトロン」のひとりでもあると思います。
ちなみに名古屋の本丸御殿は、20-30年後に屋根を葺き直す必要があるそうです。
見学に行った方は、入場料という形で、公開の運営維持費だけでなく、間接的に将来の修復基金の一部になる可能性もあります。美術品の保護のためのパトロンの一人になった気持ちで名古屋城・本丸御殿の狩野派の絵を見ると、また一味違った感慨深い旅になるかもしれません。
近隣のZEROOショップ
 |
|
A.M.I 名古屋PARCO店 460-0008 |
 |
|
SHIHO時計店(シホウトケイテン) SHIHO |
 |
|
阪急メンズ大阪 THE TIME HOUSE HANKYU MEN'S OSAKA THE TIME HOUSE |
 |
|
ベイシススピーシーズ BASIS SPECIES |
 |
|
EYE-EYE-ISUZU G-Time店 EYE-EYE ISUZU G-Time Store |
 |
|
EYE-EYE-ISUZU本店 EYE-EYE-ISUZU HONTEN |


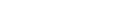










![[NEW] ZEROO M5-01 THE KIRCH MECHANICAL AUTOMATIC](http://zerootime.com/cdn/shop/files/ZM005-01SSV_{width}x.png?v=1753693052)










